「MOD使ってみたいけど、BANされたりしないか」と初心者の方からよく質問されます。
確かに、ゲームによってはMODの使用が規約違反とされ、アカウント停止の対象になることもあります。でも一方で、まったく問題なくMODを使えるゲームも存在します。
今回は、「どんなMODが危ないのか?」「どのゲームで使うとリスクがあるのか?」を、初心者向けに分かりやすく解説していきます。
前提:オフライン専用ゲームはセーフな事が多い

Skyrim、Stardew Valley、Cities: Skylinesなど、オフライン専用のゲームはMOD文化が非常に盛んです。これらのゲームでは、MODの導入が公式で許可されていたり、Steamワークショップで配布されているケースも多いです。
よほど極端なMOD(著作権ガン無視等)でなければ、BANの心配はまずありません。
| MODが基本的に許可されているゲーム例 |
|---|
| ・TESシリーズ(Skyrim、Oblivionなど) ・Falloutシリーズ(Fallout4、Fallout3など)※76は特殊な例なので除外 ・サイバーパンク2077 ・ステラブレード ・Stardew Valley ・Cities: Skylines ・RimWorld など |
オンライン対応ゲームは要注意
一方、マルチプレイがあるゲームやPvP要素のあるゲームでは、MODの使用がグレーまたはアウトになることがあります。特に対戦要素があるゲームでのチート系MOD使用はただのチーターですので絶対にNG。
- Apex Legends/Valorant/CoDなどの競技系FPS:MODは完全NG。チート扱いされ即BANされる危険あり。
- PalworldやARKのようなPvE中心のオンライン対応ゲーム:ソロやフレンド限定サーバーならセーフなケースも。
- MinecraftやTerraria → サーバーによってOK/NGが分かれる。事前に利用規約を確認しよう。
「ローカルで使う分にはOKだけど、公式サーバーはNG」という線引きがあるゲームが多いので要注意。
オンラインゲームは基本的にMOD使用NG
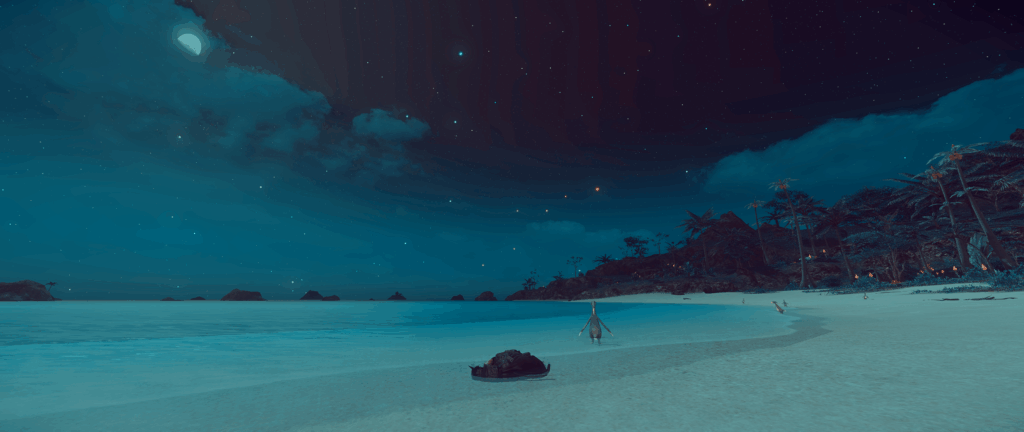
オンライン対応ゲームの中でも、対戦FPSやMMORPGのようなオンラインを前提としているゲームに関しては、ほとんどのタイトルでMODはNG扱いになっています。
MODを使うことで公平性を欠いたり、他者に迷惑をかける可能性があるなど理由は様々ありますが、公式がNGと言ったらそれが全てです。MODの利用を考えているのであれば必ず利用規約を確認しましょう。
余談ですが、先日FF14の吉田PがMODに関する声明を出していますので、オンラインゲーでMODを使いたい人は必ず目を通しておくことをおすすめします。
今回の声明や生放送での発言から、吉田P自身はMOD文化について寛容な姿勢であると発言しており、今回の声明でもその旨を改めて明言しています。その上で、更にMMORPGの責任者という立場からオンラインゲームにMODを使う事について述べられており、個人的にかなり貴重な文章なんじゃないかと思ってます。
立場的にもちろん明言はされていませんが、FF14をやっていない人でも上記の文章から「やるならバレないように、他人に迷惑がかからないようにやれ」と遠回しに言ってくれている事がわかるはず。
オンでもオフでも著作権には気をつけるべき
一方で、MODだからといって何をやっても大丈夫、というわけではありません。
特に他ゲーを扱ったMODには、著作権のリスクが潜んでいます。
たとえば『Palworld』で実際に起きた事件では、パルをポケモンに置き換えるMODが話題になった直後、任天堂からの著作権申し立てで速攻削除されました。最終的に訴えられたという話は聞いていませんが、普通に著作権侵害なので訴えられても文句は言えません。またこういったMODは作った人だけでなく、そのMODを使ったスクリーンショットをSNSに投稿した人まで訴えられる可能性がある点に注意すべきです。
これはあくまで“可能性”ですが、任天堂のような著作権保護に非常に厳しい企業の場合、ファンアートやMODすら看過されないケースもあるというのは、MOD文化に触れるなら頭の片隅に置いておいたほうが良いです。
もちろん、全ての企業がそこまで厳しいわけではありません。
たとえばSkyrimやFallout、サイバーパンクのようなゲームでは他ゲームの衣装を再現したMODが普通に流通していたりします。中には“黙認”や“実質容認”のような対応をしてくれているパブリッシャーもあります。
でも、これもあくまで「グレーゾーン」。
見逃してもらっているだけで、ある日突然アウト判定される可能性もゼロではないのです。特に有料MODだったり、注目度が高くなりすぎた場合はリスクが跳ね上がります。
つまり、「自己責任でやるもの」という意識がとても大切。
MODは自由で楽しい文化ですが、その自由は“見えない線”を越えないように使っていくことで初めて守られる、ということを覚えておきましょう。
安全にMODを楽しむためのポイント
- MODを入れる前に、そのゲームの利用規約(ToS)やFAQを必ず確認する
- オフライン専用で使うか、ローカル環境で限定的に使う
- オンラインに繋ぐ前にMODをアンインストールまたは切り替え
ちょっとした気配りと確認で、MODによるBANリスクは大きく下げることができます。
MODは確かにグレーゾーンもある存在ですが、「どこで・どんなMODを・どう使うか」さえ間違えなければ、安全に楽しむことができます。
逆に、チートMODを公式サーバーで使うのは論外。自己責任とはいえ、常識的なラインを超えないことが大前提です。
正しい知識と慎重な行動で、MODの世界をもっと安全に楽しんでいきましょう。



コメント